朝日新聞に掲載!
「現場へ! 医療的ケア児が学ぶ」という朝日新聞夕刊の連載記事の中で、もみじの家を取り上げていただきました。(2021/10/7)
「発達支援の重要性」「住み慣れた地域での就学」「地域間格差」「医療的ケア児支援法」など、大事な要素が詰まった、密度の濃い記事です。
大平記者、ありがとうございました!
https://digital.asahi.com/articles/ASPB30NVYP9SUPQJ00F.html
(全文読むには無料登録が必要です)
開通!もみじのWi-Fi
登録者の皆様
大変お待たせしました。
もみじの家のWi-Fi が、ようやく開通しました。
1階の居室やキッチンでインターネット環境が無料でお使いになれます。
ユーザーIDやパスワードは、もみじの家の中に掲示してあります。
ハウスマネージャー内多勝康
世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)HP開通!
8月に開設した世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)のHPが公開されました。
センターの業務内容や利用方法、ブログ、スタッフ紹介など、役立つ情報がそろっていますので、ぜひ一度、お立ち寄りください。
https://hinatabocco2183.wixsite.com/setagaya
【11/1まで】東京都医療的ケア児(者)実態調査へご協力ください
都内在住の登録者の皆様
東京都より、下記の調査について協力要請がありました。
今回の調査は、都が実質的に初めて行う医療的ケア児(者)実態調査で、今後の施策展開において非常に重要な調査になると考えているとのことです。
ボリュームのある調査ですが、お時間が許せば、御協力いただきますようお願い申し上げます。(医療的ケアが必要な40歳未満の在宅の都民の方が対象です)
調査回答WEBページは、こちら
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1624449969605
チラシは、こちら
https://home-from-home.jp/systems/wp-content/uploads/2012/10/367c51301fe39373d8dcf3e8a05d9e31.pdf
<問い合わせ>
株式会社 名豊
電話:052-322-0074 ※午前9時~午後5時まで(日・祝除く)
E-mail:chosa@meihou-c.co.jp
【朗読】医療的ケア児支援法
2021年9月18日施行の「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」を元NHKアナウンサー(内多)が朗読しました。
この法律は、日本をインクルーシブ社会に導く、大きな力を秘めています。
なかなか全文を読む機会のない法律ですが、朗読を聞くことで、この法律の素晴らしい理念が多くの方々に伝わることを願っています。
こちらをクリック! ⇨ 【朗読】医療的ケア児支援法 - YouTube
なお、理解しやすくするため、一部、表現を変えているところがあります。
国立成育医療研究センターもみじの家ハウスマネージャー 内多勝康
【8/21放送】医療的ケア青年がNHKスペシャルに登場します!
医療的ケアを必要とする青年が、NHKスペシャルに登場します!
番組は、8月21日(土)夜9時~総合テレビ「TOKYOカラフルワールド~香取慎吾のパラリンピック教室~」
ぜひ、多くの方にご覧いただきたいと思います。
その青年は、もみじの家が3年前に企画した「医療的ケア児と家族の主張コンクール」でグランプリを獲得しています。
https://www.youtube.com/watch?v=P8foXYTgyHQ&t=14s
医療的ケアの世界に、また新たなページが刻まれます。
皆さんも、歴史的番組を目撃してください!!
【印刷自由】世田谷区医療的ケア相談支援センターリーフレット
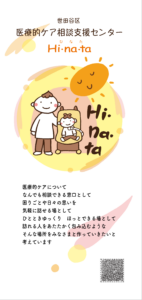 世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)が8/3にオープンしました。
世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)が8/3にオープンしました。
困りごとや日々の想いを気軽に話せる場、忙しい日々を送る保護者がゆっくりほっとできる場、また医療的ケアを必要とするご本人やご家族の憩いの場として、医療的ケアに関わるすべての人を優しくお迎えします。
事業内容や利用方法などを載せたリーフレットが、こちらからご覧いただけます。
https://home-from-home.jp/systems/wp-content/uploads/2012/10/851f2bebebd821282cdaf7ac4ab6ead4.pdf
印刷、配布は自由です。
おうちで体験!夏休み社会科見学
オンラインで工場や会社の見学ができるプログラムのご案内です。
「ポテトチップスのできるまで」や「動物の毛を電子顕微鏡で見る」「アルミ缶リサイクルについて」など、なかなか見られない内容が盛りだくさん!
参加費は無料で、Jリーググッズが当たる抽選会もあります。
対象は小学生と中学生で、どこにお住まいでも参加できます。
期間は、8月19日(木)と20日(金)の2日間。
申込期限は8月6日ですが、先着順ですので、お申込みはお早めに!
詳しいプログラムは、こちら
https://home-from-home.jp/systems/wp-content/uploads/2012/10/962af73f909568842e4fa05dafd1d9d5.pdf
申込方法は、こちら
https://home-from-home.jp/systems/wp-content/uploads/2012/10/5dcbbedcc63ada0dba750d6bc50efbea.pdf
【8/3世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)開設!】見学会のお知らせ
世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)が、いよいよ令和3年8月3日にオープンします。(紹介動画も公開されました!https://youtu.be/Ruv6EFIuX4o <s://youtu.be/Ruv6EFIuX4o)
8/3の13:30~14:30は、センター内を自由にご見学できます。地図はこちらです。
https://home-from-home.jp/systems/wp-content/uploads/2012/10/omote-1.pdf
*当日10時~オンラインにて開設式典を配信します。詳しくは、こちらをどうぞ。
開設式典【世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)】 | 世田谷区ホームページ (setagaya.lg.jp)
【7/16締切】開設イベント参加者募集中!世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)
世田谷区医療的ケア相談支援センターHi・na・ta(ひなた)が、いよいよ令和3年8月3日より事業を開始します。(紹介動画も公開されました!https://youtu.be/Ruv6EFIuX4o <s://youtu.be/Ruv6EFIuX4o)
そのオープニングイベントに参加するご家族を募集中です。
申込締切は、7/16(金)です。
ご参加いただいたみなさんで作るハンドスタンプ・アートや、Hi・na・taのロゴ入り風船のプレゼント、スポーツ選手との交流イベントなどをご用意して、お待ちしています。
(感染予防を行い1組あたり5~10分程度)
お子さんが楽しめるような内容ですので、ぜひきょうだいの方やご家族一緒にご参加ください。
*当日10時~オンラインにて開設式典を配信します。
